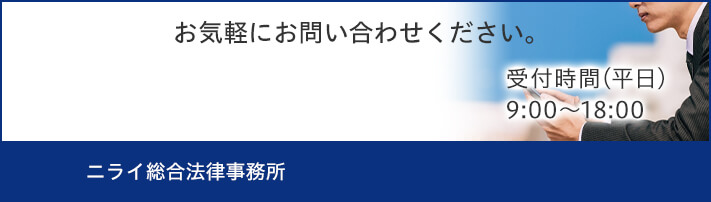1 業務命令とは
雇用契約は、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する」契約です(民法623条)。
しかし、業務内容は大枠では予め合意できても、具体的な内容はその都度の指揮命令によって確定せざるを得ないため、「労働に従事することを約」することの中には、使用者に指揮命令権を付与することの承認が含まれており、労働契約の本質的要素となります(最高裁昭和61年3月13日判決・労判470号6頁参照)。
使用者が労働者に対して持つ指揮命令権の行使を、一般に業務命令と呼びます(どのような範囲の権限を業務命令権と呼ぶかについて議論はあります)。
ここでは業務命令一般について解説し、業務命令の中でも問題になりやすい時間外労働命令や、転勤、配転、出向等の命令について個別には取り上げません。
▼類型別問題社員対応の関連記事はこちらから▼
企業に対する誹謗中傷を行う問題従業員への対応方法について弁護士が解説
2 業務命令の有効性、適法性
業務命令の有効性、適法性は、一定の業務命令の無効確認や(例えば配転命令等)、業務命令に基づく懲戒処分(懲戒解雇含む)や普通解雇の無効確認、違法な業務命令に対する不法行為ないし債務不履行を理由とする損害賠償請求といった形で問題となります。
上記のとおり、業務命令の根拠は雇用契約(使用者と労働者の合意)に求められるところ、業務命令はあくまでも労働契約で合意された範囲内でのみ可能であり、権利濫用等の一般法理も適用されます(労契法3条4項、5項)。
したがって、業務命令を行う際、あるいは業務命令違反を理由とした対応をする場合には、以下のような点に気を付けなければなりません。
⑴ 労働契約の範囲内かどうか
大前提として、そもそもの労働契約の内容を把握する必要があります。
雇用契約書、周知された合理的な就業規則(労契法7条)、労働協約、労使協定等を踏まえて、どのような内容の労働契約が締結されているか、ということの把握が必要です。
労働契約外の業務命令は当然無効であり、労働者には従う義務がありません。
純粋に私生活上の事項について業務命令をすることはできませんし、労働契約において業務内容が特定されている場合には、それと異なる業務内容を指示することもできないことになります。
ただし、就業規則に配転命令の規定がある等、業務内容を変更することも契約内容となっていると評価できる場合は、次項以下の問題がなければ業務内容の変更を命じることができます(逆に言えば、配転命令に契約上の根拠がない場合は、労働契約において特定された業務内容と異なる業務内容を指示することはできません)。
いずれにせよ、業務命令に労働契約上の根拠があるかどうか(業務命令が労働契約の範囲内か否か)がまず問題となります。
⑵ 命令する業務の適法性
仮に労働契約上の根拠があっても、具体的に命じた行為が違法行為である場合、業務命令は無効となり、使用者に、労働者に対する不法行為責任が生じます。
このような点から業務命令の有効性、適法性を問題とした裁判例としては、例えば、居宅介護支援事業等を行っていた会社が市に提出する書類の改ざんを命じた行為が違法な業務命令とされた大阪地裁平成18年9月15日判決・労判924号169頁があります。
⑶ 強行法規に反する命令
仮に労働契約上の根拠があっても、業務命令が強行法規に反する場合には、業務命令は違法、無効となります。例えば、組合所属、思想、性別などを理由とする差別的な内容をもつ業務命令は、強行法規違反として(労組法7条1号、労基法3条、雇用機会均等法6、7、9条)、違法、無効と解されます(バス会社が2つある労働組合のうち片方だけに新車の配車をした行為が労働組合法7条の不当労働行為に該当し、他方組合及び組合員に対する不法行為を理由とする損害賠償を認めた広島高裁平成6年3月29日判決・判タ868号189頁(最高裁平成9年6月10日判決・労判718号15頁により維持)など)。
個別の業務命令についての規制としては、例えば労基法36条2項の規律に反する時間外労働命令は違法、無効と解されます。
⑷ 権利濫用(労契法3条5項)
例えば、懲罰目的でなされる労働者の人格権を侵害するような業務命令など、権利濫用反といえるような業務命令は違法、無効であり、不法行為になると解されています。権利濫用といえるかどうかは、主として、目的と態様の観点から判断されています。
権利濫用と評価された例としては、国労マーク入りベルトを着用して就労した組合員に対する就業規則の書き写し命令(最高裁平成8年2月23日判決・労判690号12頁)、組合専従復職後の組合員に労使協約に反してコーヒー回収作業やメモ用紙作成作業に従事させた行為(大阪高裁平成2年7月10日判決・労判580号42頁)、JR西日本が日勤教育として業務上の必要性なく車両天井清掃、除草作業をさせた行為(大阪地裁平成19年9月19日判決・労判959号120頁)、ウサギの耳の形をしたカチューシャ等のコスチュームを研修会で着用させた行為(大分地裁平成25年2月20日判決・労経速2181号3頁)、労働者の生命、身体に予測困難な危険をもたらす危険海域への就航命令(最高裁昭和43年12月24日判決・民集22巻13号3050頁)などがあります。
業務命令を行う場合、その目的に業務上の必要性があるかどうか、懲罰目的がないか、無意味なものではないか、業務上必要な程度を超えて労働者に身体的、精神的苦痛を与えるものといえないか、不可能を強いるものではないか、といった観点から注意を払う必要があります。
なお、このような観点からは、例えば労契法3条3項のワークライフバランスへの配慮等の規定のような抽象的な規定も、一定の機能を果たすことになります。
3 業務命令違反への対応
⑴ 指導指示
上記のとおり、雇用契約の本質から、労働者は適法な業務命令に従う義務を負っていますので、業務命令に従わない場合、債務の本旨に従った履行を労働者が行っていないことになります。
そのため、使用者は、労働者に対して、業務命令に従うよう指導、指示をすることができ、それでもなお従わない場合は後述するような対応をとることができます。
そもそもの業務命令や、業務命令違反への指導、指示にあたっては、上述してきたことも踏まえて、以下のような点に注意を払う必要があります。
具体的には、①業務命令や指導指示が雇用契約の範囲内の指示であること、②業務上の必要性がある業務命令、指導指示であること、③相当性がある業務命令、指導指示であること(必要な限度を超えて身体的、精神的な苦痛を与えるものでなく、人格を侵害したり、人格を非難するようなものではないこと)、④組合所属、思想、性別などを理由として差別的な取り扱いをしないこと、その他強行法規に反しないこと、⑤違法なことを命じ、あるいは指導指示しないこと、⑥個別具体的に業務命令を行い、あるいは業務命令違反がある場合、都度、個別具体的な違反を指摘して従うよう指導、指示すること、⑦記録に残すことなどが重要です。
①~⑤については、概ね上で述べたとおりです。⑥については、適時に個別具体的に業務命令を行うことが重要です。内容が抽象的に過ぎると、そもそも業務命令がどのようなもので、何をすれば従っていることになるのかについて共通の認識を形成できません。
また、目標と業務命令は区別する必要があります。例えば、営業職の労働者に、通常の労働時間に通常の勤務態度で就労しても達成できるか不確実なノルマを課したとしても(例えば、1ヵ月で何件の成約をすること)、このノルマそれ自体は業務命令とはいえない単なる目標であり、ノルマ不達成を業務命令違反と評価することはできません。
どこにどのような形で営業を行ったか報告を行うよう指示する、とか、通常の労働時間に通常の勤務態度で就労することで達成が可能な業務の指示にブレークダウンして(例えば、特定の業者に営業電話をかける)指示する、といったことが必要です。
業務命令違反に対して、指導、指示する場合も、指示違反後、時間を置かずに、具体的に指摘して注意する必要があります。
⑦については、業務命令について共通認識をもって円滑に業務を進めるためにも、あるいは、事後的に業務命令に起因する紛争が生じた場合に、業務命令を行っていたという事実や、その内容が争われた場合に備えるために、記録が残るように業務命令をし、あるいは指導、指示をすることが望ましいです。
例えば、書面やメール、社内チャット等によることがありえます。
書面で指導、指示を行う場合は、書面を交付したこと自体も残る形(例えば、当該書面の写しに、書面の交付を受けた、という署名、押印を要求する)が望ましいです。
ただし、書面によるのは煩雑ですので、日常的にはメールや社内チャット等で業務命令をし、あるいは指導、指示を行い、重要な業務命令を行う場合や、厳重に指導、指示を行うような場合に、書面で行えばよいでしょう。
⑵ 懲戒処分
業務命令違反が懲戒事由とされている場合(就業規則に規定がある)、労働者の業務命令違反を理由として、懲戒処分を行うことができます。
ここでは、業務命令違反を理由とするものに限られず、懲戒処分一般について概説します。懲戒処分について詳細を述べることはしません。
一般に、懲戒処分が有効であるためには、①あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定め、周知していること(最高裁平成15年10月10日判決・労判861号5頁:なお、労基法89条9号)、②就業規則上の懲戒事由が存在すること、③懲戒権の濫用にあたらないこと(労契法15条)が必要とされます。①については、「正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき」に懲戒処分を行うことができる、というような規定が一般的です。
なお、新設ないし改定した就業規則の条項を遡及的に過去の行為に適用して懲戒処分を行うことは許されません(遡及禁止)。
②は①により契約内容となっている懲戒事由が存在することにより、懲戒権が発生することになり、①と②があることで、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」(労契法15条)にあたることになります(最高裁平成18年10月6日判決・労判925号11頁参照:ただし、学説上、②の位置づけには議論があります)。
③については、客観的に合理的な理由の有無、社会通念上の相当性が問題となります(労契法15条)。
客観的に合理的な理由とは、就業規則の懲戒事由該当事実があるとしても、懲戒処分を行う客観的に合理的な理由がなければならないというもので、濫用審査の要素と解されています(ただし、学説上、位置付けについては議論があります)。
例えば、上記の平成18年最高裁判決の事案では、就業規則の懲戒事由に該当する事由があったものの、行為から7年を経過してなされた懲戒解雇について、客観的に合理的な理由がないとして無効と判断されています(この判決自体は労契法15条が制定される前のものですが、この判決等の判例法理が立法により明確化されたのが労契法15条等の規定です)。
社会通念上の相当性は、以下のような視点から問題となります。
まず、行為と処分の均衡です。要するに、行為に対して重すぎる処分は許されません。
労契法15条が「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして~社会通念上相当であると認められない場合」に濫用とされる旨を規定しているのは、その趣旨と理解されています。
懲戒処分の種類としては、けん責、戒告、厳重注意、減給(労基法91条の制限がある)、出勤停止・停職、降格、降職、降給、昇給停止、懲戒解雇などがありますが、業務命令違反の程度が軽微である場合には、懲戒処分もそれに均衡した軽いものでなければなりません。
特に、懲戒解雇は、労働者に多大な不利益を生じさせるため、特に重大な理由がなければできません(この観点から懲戒解雇が重きに失するとして無効と判断した例として、東京地裁平成21年4月24日判決・労判987号48頁、東京地裁平成28年7月19日判決・労判1150号16頁、前橋地裁平成29年10月4日判決・労判1175号71頁等)。
この観点からは、就業規則上も、懲戒処分の種類ごとに懲戒事由を区別していることが多く、また望ましいといえます。
軽微な事由については、軽い懲戒処分を行った上で、それでも改善が見られないような場合に、退職勧奨、解雇を検討すべきです。
次に、懲戒処分が相当といえるためには、他の労働者との公平性も求められます。もとより、厳密な比較は困難であるとしても、明らかに他の労働者と公平を害する懲戒処分は相当性を欠くものと解されるおそれがあります(この観点から懲戒解雇を無効とした例として東京地裁平成11年12月17日判決・労判778号28頁、東京地裁平成17年11月22日判決・労判910号46頁等)。
その他、同じ懲戒事由について二度懲戒処分を行うことは許されず(二重処分の禁止:東京地裁平成10年2月6日決定・労判753号47頁等)、懲戒手続は適正でなければなりません(就業規則等に定める手続が履践されていること、特に重い処分の場合は弁明の機会が付与されていることが必要です)。
手続的規律を実施していない場合には、そもそも、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」(労契法15条)に当たらないと解することもできます。
▼関連記事はこちらから▼
従業員を解雇する具体的な要件について弁護士が解説~普通解雇とは?~
⑶ 退職勧奨
業務命令に従わないことで会社の業務に支障が生じている場合、当該労働者に退職を勧奨することがありえます。退職勧奨とは、辞職を勧める使用者の行為、あるいは使用者による合意解約の申込みに対する承諾を勧める行為で、これ自体は基本的には自由になしえます。
しかし、差別的な取り扱いをした場合や(雇用機会均等法6条4号は退職勧奨について明示していますが、労組法7条や労基法3条についても問題となりえます)、退職勧奨の手段・方法が、社会通念上相当と認められる限度を超えている場合は、違法とされ、不法行為と評価されることがあります。
そのため、退職を勧奨する場合は、あくまでも労働者の自発的な退職意思を形成するために行うものであることを理解し、虚偽を述べたり、脅迫的な言辞を用いたりせず、労働者が勧奨に応じない場合には、それ以上の勧奨は行わないことが肝要です。
⑷ 解雇(懲戒解雇、普通解雇)
ここでは、必ずしも業務命令違反に限定せず、懲戒解雇、普通解雇一般について概観します。解雇について詳細を述べることはしません。
一般に、解雇が有効とされるためには、まず、解雇禁止期間(労基法19条)や解雇禁止事由(労基法3条、104条、労組法7条、雇用機会均等法8条、育児介護休業法10条、16条等)に該当しないことが必要です。
その上で、原則として30日の解雇予告あるいは解雇予告手当の支払をした上で(労基法20条)、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要とされます(労契法16条:懲戒解雇については、労契法15条と16条が重畳適用されるという見解が有力です)。客観的に合理的な理由とは、解雇を正当化するだけの理由が必要ということで、解雇類型(例えば整理解雇等)ごとに判例法理が積み上げられています。
なお、労基法89条3号が解雇事由を就業規則の記載事項としたこととのかかわりで、「その他前各号に準ずる事由が生じたとき」といった一般条項を就業規則に記載していないような場合に、就業規則に記載されていない理由での解雇が許されるかについては争いがあります。
学説の多数は限定列挙説をとっており、同説によるなら解雇事由に該当しない理由での解雇は無効とされるため、一般条項を設けることが望ましいといえます(なお、懲戒解雇については、就業規則に記載されていない事由を懲戒事由としても当然に無効です)。
業務命令に従わない労働者に対しては、当該事由を懲戒事由とする懲戒解雇や、労働者の適格性の欠如等を理由とする普通解雇が問題となりえます。
懲戒解雇として有効とされずとも、普通解雇としては有効であるとされる場合があるため、懲戒解雇を行う場合も、予備的に普通解雇としても行うことが望ましいです。
社会通念上相当であることについては、上記で懲戒処分について触れたような観点が問題となります(この点を明確に示した裁判例として最高裁昭和52年1月31日判決・労判268号17頁)。
また、解雇については、労働者から請求があれば解雇理由証明書を交付しなければならず(労基法22条)、事後的に解雇理由を追加することは許されないという見解が有力ですので、解雇前に解雇事由について十分検討することが重要です。
▼関連記事はこちらから▼
問題社員対応(モンスター社員対応)~解雇・退職勧奨について弁護士が解説~
退職勧奨による退職は企業都合になりますか?自己都合の退職との違いについても弁護士が解説!
4 弁護士への相談について
業務命令の有効性、適法性は、当該労働者との交渉や労働審判、民事訴訟、保全処分といった手続において、労働者から、配転命令等の一定の業務命令の無効確認や、業務命令に基づく懲戒処分(懲戒解雇含む)や普通解雇の無効確認、違法な業務命令に対する不法行為ないし債務不履行を理由とする損害賠償請求を受ける形で問題となります。
上述してきたような点を踏まえて業務命令をし、業務命令を遵守するよう指導、指示を行い、適切な手続をとって軽微な懲戒処分を経て重大な懲戒処分や懲戒解雇、普通解雇を行えば、このような労働者からの請求を予防し、あるいは労働者から請求を受けても会社の利益を守れると考えられますが、気を付けなければならないことは非常に多いです。
また、そもそも就業規則に懲戒事由や解雇事由を規定していなかった、一般条項を規定していなかった、就業規則を周知していなかった、業務命令や指導指示を記録していなかった、解雇理由証明書を発行してしまったので理由が追加できない等、紛争になってしまった後からは、取り返すことができない、あるいは困難な場合もあります。
問題社員への対応、特に、最終的に退職勧奨や解雇を行うに際しては、事前に弁護士に相談することを検討ください。
Last Updated on 2024年10月22日 by roudou-okinawa
弁護士法人ニライ総合法律事務所は、実績豊富な6名の弁護士で構成されています。このうち3名は東京で弁護士活動してきた経験を持ち、1名は国家公務員として全国で経験を積んできました。 当事務所の弁護士は、いずれも「依頼者の最大の利益を追求する」をモットーに行動いたします。 |